お子さんが、バイリンガルになることを薦める記事ではございません。
こんにちは、子育てをしながらイギリスの大学院にオンライン留学し、無事にTESOL修士号を取得しましたbubumiです(╹◡╹)
今回は改めて自己紹介を兼ねて、「バイリンガルになるために」をテーマにしました。イギリスの大学院のTESOL(英語が母国語でない学習者への英語教授法)で学んだ知識をもとにお伝えします。お子さんがバイリンガルになるにはどんなことをしたら良いのかなと考えていらっしゃる親御さんへのヒントとなれば、という記事です。特に現在、海外在住でお子様が帰国子女になるけれど、英語力維持にはどうしたら良いか困っている方は必見です。日本在住の方でも、バイリンガル育児をしたい親御さんへのヒントとなるはずです。
(※バイリンガルが良いと薦めている記事ではございませんのでご了承ください。)
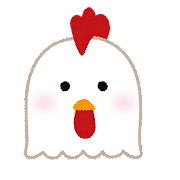
- 帰国子女なのに英語が話せなくなる理由は?
- 自分の子どもをバイリンガルに育てたいけど、どうすればいい?
- 駐在先から帰国後、子どもの英語力を維持するには?
- 自己紹介:帰国子女なのに英語が話せませんでした
- バイリンガルになれなかった9つの原因&親が知っておくべきこと
- 大人になってから英語が話せるようになりました
1. 自己紹介:帰国子女なのに英語が話せませんでした
私は、ほぼ6歳になるまでイギリスにいましたが、バイリンガルになれませんでした。いわゆる帰国子女なのに英語が話せない現象です。「帰国子女」は文科省、総務省、入試における各学校の定義など様々ありますが、ここでは一般的な辞書での広い意味で表現させてもらいます。
帰国子女(きこくしじょ)とは、保護者の仕事やその他の理由で海外に滞在し、後に日本に戻ってきた子供たちのことを指す。 (引用:実用日本語表現辞典)
そんな私の英語力の変遷を簡単にご紹介します。
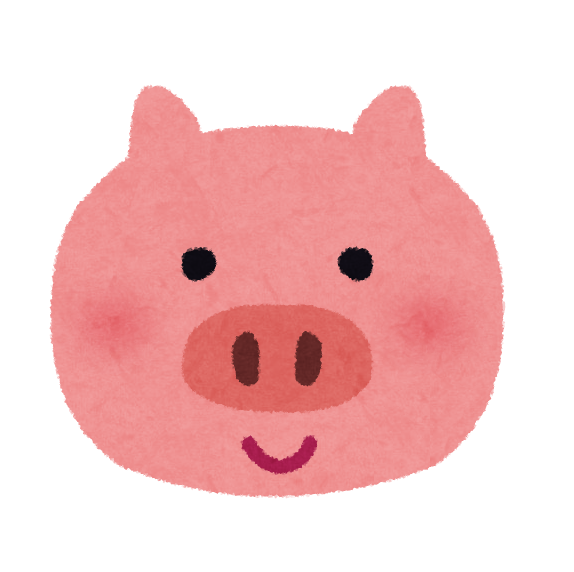
私の英語履歴
- 0~5歳:イギリス在住。現地の幼稚園でスコットランドアクセントの英語を習得。家庭内では日本語使用。
- 6~8歳:日本の公立小学校に通いながら、週1回の英会話スクールに通う。
- 9~11歳:英語にほとんどふれない生活。中学受験勉強に必死の日々。
- 12~14歳:中学校の英語の授業で英語が得意科目に。
- 15~18歳:高校で英語力が停滞するも、大学受験では得意教科としてなんとか逃げ切る。英検準1級を取得。
- 19~26歳:英語をほぼ使わない生活。
結果「バイリンガル」にはほど遠い状態に仕上がりました。私は中高時代に帰国子女枠で入学してくる友達がいる学校で過ごしました。そこで、

自分より海外滞在期間が短いのに、バイリンガルになれている友達もたくさんいる。何が違ったんだろう?
と思っていました(かといって英語の勉強をすごくするわけではなかった)。
TESOL(英語を母国語としない学習者への英語教育)を専攻し、修士号をおさめたのは、自分がバイリンガルにならなかった原因を論理的に知りたいと思ったのもひとつの要因でした。大学院を終え、今ではおかげで解明しました。
30半ばにもなり自己分析結果を公開するのもなんだかダサい気もしますが、同じようにもし帰国子女という背景がありながら英語学習に悩んでいる方がいたり、お子さんが帰国子女だけれど日本に戻っても英語力を維持させたいとお考えの保護者の方のヒントになればなと思い、記事にさせていただきます。
2. バイリンガルになれなかった9つの原因&親が知っておくべきこと
原因1 英語にふれる量が少なかった
第一に大切なこととして、バイリンガルになるには、その言語に毎日4-5時間以上ふれている必要があります。この必要な時間に関しては諸説あり、断定するのを好まない研究者もいます。しかし、大学院の授業の先生から学んだ内容、また周囲のバイリンガル育児を提唱している方数名の方々の検証でおおよそ、この数値は必要量として近いと思われます。皆さんも、毎日1時間英語を聞いて話しているだけではバイリンガルになれないのは容易く想像できると思います。ある程度の量は必要ということです。
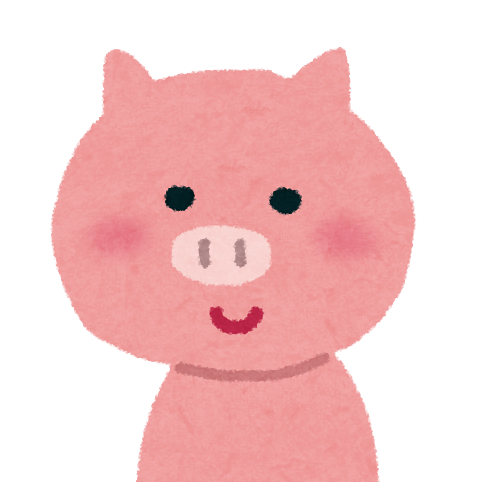
私は6歳で日本に戻ってから、日本語に囲まれる生活で、唯一英語を話していたのは、週に1度英会話の先生とのみだった…
よって、英語にふれる絶対量が足りませんでした!
英語には1日あたり4-5時間ふれる必要がある。
原因2 interactionが必要だった
質の面でも不足していました。言語習得において、「聞く・話す」両方が大切なのはもちろんなのですが、interactする(会話のやりとりをする)という観点もとても重要です。
理解可能なインプット(i+1)とそれを到達するための補助(scaffoloding)が言語能力を向上させる鍵
インプットだけでなくアウトプットの必要性
インプットに加えて、相互のやりとり、フィードバックを含めたやりとり(interaction)が重要
赤ちゃんとお母さんとのやりとりを思い浮かべてみてください。赤ちゃんがお母さんを見て、「マ」といえば「うん、ママだよー!」「よく言えたねー!」など反応(フィードバック)をすると思います。これによって赤ちゃんは「ママ」でいいんだ、という気づきが起こります。また違う場合にはそれを修正してもらうことで、ちがうんだという気づきとともに修正された情報がインプットされます。
インプット⇨アウトプット⇨フィードバック=気付きが起こる
言語習得には、この過程が必要です。
動画を一定時間見るだけ=インプットのみでは学習者が言語を話せるようにはならないのはこうした理由からです。
インプットだけではだめ。アウトプットだけでもだめ。英語でやりとりをすることが必要。
原因3 英語への興味がもてなかった
こちらは想像しやすいと思いますが、言語学習の成功には、動機付け(motivation)が重要です(Gardner & Lambert, 1972)。英語に興味をもっていなくてはうまくいきません。
日本に戻って誰も英語を話さない環境でした。唯一話すのは、英会話スクールの大人の男性の先生のみ。学習のための英語で、学ぶ意味や楽しさを子供なりに全く感じられていませんでした。
ここで無理に学んだ経験で英語学習への内発的動機(intrinsic motivation)を損ない、英語に対する興味を薄れました。
子供によって興味のもち方は異なると思います。友達と話すことで興味をもつ子もいれば、歌や本が楽しめる子、スーパーヒーローやプリンセスに関しての動画を英語で見ることが楽しみにできる子供。
子に応じて興味をもつきっかけを見極める。言うは易く行うは難しで、これが一番難しいかもしれません。
英語が楽しいと思える環境づくりが必要。興味をもてることは子それぞれ。
原因4 ふれる英語が“本物”でなかった
ふれる英語はauthentic(本物/自然)であることが理想です。これはネイティブ英語であるという意味ではありません。
- 遊び
- 絵本
- 歌
- ゲーム
- 友達との交流
- クラスで他の友達と学ぶ
英会話スクールで大人の先生と1対1でのみ英語を話す環境は…子供にとって自然な英語習得の形ではなかったのです。
もしも年齢が上がり、高校生のお子さんを考えてみると、今度は上記した活動は少し不自然にもなってくるでしょう。高校生にとっての“本物の/自然な英語”とは、遊びやキッズソングではないでしょう。流行の洋楽、ゲームや友達との交流が自然になってきます。クラスで他の友達と学ぶ、この学び方にもディスカッションやネットにある情報を見たり動画を見たり、ということが含まれてきそうです。さらに、年齢に合った本を読むことも本物の英語にふれる自然な形でしょう。(問題は、年齢に合う本の英語レベルが学習者に合わないことが多い…)
年齢に応じた“本物の英語”/“自然な英語”は変わるということ。年齢に応じた“本物の英語/自然な英語”にふれさせる必要がある。
幼少期の子供→読み聞かせや遊び。
幼稚園や小中学生くらい→教室で先生から英語を聞いて友達と一緒に声を出したり、友達との遊びんだりする中で学ぶ英語
高校生以上→小説を読んだり、友達との意見交換、ネットを活用した英語など。
原因5 学び方の変化に対応できなかった
言語の学び方は、子供と大人(青年期から)で変わります。
「暗黙的学習(implicit learning)」子供
↓
「明示的学習(explicit learning)」大人
に変化します(Ellis , 2008) 。この移行を理解し、適応することが必要です。
「暗黙的学習」
文法などの説明なしに歌や会話などの中から自然と吸収する
「明示的学習」
文法などの説明を明らかに与える
文法などの説明があった方が大人にはわかりやすく言語が学びやすくなります。
ではこの境目がいつか。
個人差がありますが、12,13歳と言われています。
つまり中学生の時期。高校生では完全にexplicit learningが適している時期に移行しています。
私は、少し他の人より英語ができた状態で中学に入学し、文法より勘に頼っていました。むしろ文法を聞いてもどういうこと?という感じでした。なので、文法の基礎事項を右から左に流して聞いていました。すると、高校からはその学び方では通用しなくなってきました。
しかし、高校から文法を学ぼうとすると、時すでに遅し。よくわからない文法用語で溢れていてついていけなくなりました。さらに、私にはimplicit learningがあっているんじゃないか、でも文法も学んだ方が良さそう、というどっちつかずの葛藤がありつつ迎えた大学受験。
explicit learningに移行する必要があることをしっかりと心得ることができていれば、葛藤なくもう少し順調に英語力を伸ばしていけたと思います。
年齢によって言語の学び方がimplicit learningからexplicit learningに変わることを知り、子供にも伝えておく。
原因6 発音の綺麗さだけで満足していた
発音がクリアであることは英語学習のほんの一部に過ぎません。
また発音の良し悪しを日本人のほとんどは発音の一部の要素のみで判断しています。「L/Rの区別ができる」「thの発音ができる」など。これらは発音のsegmentalという要素です。私はこの要素ができているだけで、先生・親・友達からすごいね、と言われ、自身でも英語の発音は完璧!と勘違いしていました。
発音には、文全体を通してのリズムやイントネーション、ストレス(suprasegmentalという要素)も大切になります。
つまり、英語という言語の一部の発音という要素、発音の中でもsegmentalというほんの一部が人よりもできる、ということだけで、自信過剰になっていたのです。
また、発音の良さに満足し、それ以外のスキルを磨かなかったことが、英語力の停滞につながりました。
私が知るべきだったのは、発音が英語学習の全てではないということです。単語、文法、場面に応じた使い方、イディオム、様々な側面があること、それら全てを大人レベルにブラッシュアップしていく必要性を知らなくてはいけませんでした。
帰国子女の周囲の人はおだてすぎに注意をする必要があります。
特に、発音の良さは小さい子供は努力して身につけるものではなく自然とできることです。発音ではない、努力して本人が伸ばしてきた部分の英語力に焦点を当てて褒めてあげることが大切です。
発音は英語学習のほんの一部の要素。子供が発音の習得が得意なのは当然なことで、その環境を用意できた自分(親)を褒めよう。子供には、本人が努力して伸びた部分を褒めること。
原因7 幼少期に身につけた英語力が自然に戻ると過信していた
Critical Period Hypothesis(Lenneberg, 1967)では、言語習得には臨界期があり、この時期を過ぎるとネイティブレベルの習得が難しくなるとされるという仮説は有名です。【※ただし、現在はこれは発音に限ったことで、それ以外の要素の言語習得に関してはどの年齢でも達成可能だという説が多くなってきています。】
しかし、これはある時期までに習得すればそれを一生身につけていられるという意味ではありません。言語は使わなければ忘れます。
また、子供は簡単にそれを忘れていきます。
私の例では、6, 7歳では少し英会話スクールで使っていたもののそのあとは、全く使わず。中学から高校で学ぶ受験英語は発話はほとんどなく、聞いたり書いたりしている時間がほとんどだったので、英語で考える力や、スピーキングに関しては完全に忘れ去られてしまいました。
一方で、残る力は音を聞き分ける力とその音を発音する力です。
これは英語力のほんの一部の要素でしかありません。
これまで述べたように、1日4, 5時間の英語量の確保+英語のやりとり(インタラション)を続けなければ、音を聞き分ける力と発音する力以外の言語能力は忘れられていきます。
言語は使わなければ容易く忘れられていく。子供は覚えるのが早く忘れるのも早い。残るのは、音を聞き分ける力と個々の音を自分で発音できる力のみ。
原因8 幼少期に身につけた英語力を過信していた
日本人の5歳の子を思い浮かべてください。その子の日本語レベルで仕事はできるでしょうか。また、大学に行って大学生と話したり、講義の中でディスカッションしたり、レポートを書いたり。
5歳児レベルの語学力で、これらをおこなうことは、不可能です。
私がイギリスにいて、身につけた英語は所詮5歳の子が話すレベルの英語。大人になって、急にビジネスの場で生かせるレベルではないのです。
母語話者でも母語については年齢が上がるにつれ、発達させていきます。
つまり、英語を継続して勉強し続けなければならなかったのです。国語をずっと勉強してきたように。それを「私は他の日本人より英語が多少できるわ、ふふん」とあぐらをかいて勉強せずにいれば、どんどん他の勉強してきた人たちに抜かされていくのは当然のことでした。
私は言語は常に学習しレベルアップしていく必要性があることを理解しておくべきでした。
言語は学び続けていくもの。英語ができると過信し一時休めば、簡単に年齢不相応の英語力になっていく。
原因9 個人差
これを言ってしまえば元も子もないのですが、言語習得には、記憶力、性格、学習スタイルなど、個人差が大きく関わります(Dörnyei, 2005)。
言語が習得されるメカニズムは、概ね解明されています。
まずinputにはauthenticでinterestingなものが必要であること。この知識がworking memory→short term memory→long term memoryと移行したときに自分の力になります。そしてinputだけではなく、feedbackを含めたinteractionが必要だということ。ここでnoticing気付きが起こることが、より効率よくlong term memoryへと移行することに役立ちます。
しかし、これら全ての過程に個人差があります。
短期記憶するのが得意な人もいればそうでない人もいる。短期記憶から長期記憶へ移行するのにかかる時間や要する頻度も個人差がある。フィードバックも直接的な助言で効率が上がる人もいれば、モチベーションが下がる人もいる。そして、インプットの内容で興味をもてる分野は人それぞれ異なる。
ですから、この方法で皆一様に英語がペラペラになれますという黄金の方法はないわけです。
私の場合、5歳でイギリスを離れてバイリンガルになれなかった失敗原因は上記8つを挙げてきました。しかし同様に5歳でイギリスを離れても、日本の学校での勉強が合って興味を継続し英語力を伸ばしていける人もいるでしょう。結局は、個人差も大きく影響します。
言語習得には個人差が大きく関わる。これをすれば必ずバイリンガルになる!といったone-size-fits-all(万人共通の方法)はない。英語に興味をもつポイント、どういう学び方が適しているかは親が探してあげる必要がある。
3. 大人になってから英語を話せるようになりました

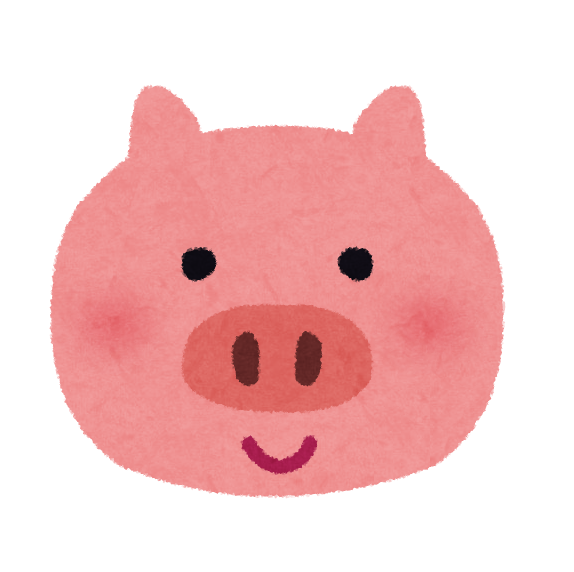
私の英語履歴その後
- 27-28歳:英会話スクールGabaに通いスピーキング向上に注視。
- 29歳:個人レッスンでスピーキング+ライティング向上。
- 30-31歳:オンライン英会話を毎日30分。
- 32歳:オンライン英会話毎日30分を継続しながら、IELTSの勉強。スピーキング5.5→6.5。イギリス大学院オンライン留学開始。
- 33-35歳:海外へ移動し生活言語を英語主流にする。イギリス大学院修了。
こうして34歳くらいの頃には、英語を話すことに緊張もせず、初対面の人とでも全く問題なく話せるようになりました。ネイティブ同士の会話はいまだに聞き取れない時もあり、聞き直すことはありますが、海外の友人がたくさんでき、子育ても英語も活用できていて、世界が広がっています。
私が使用してきてスピーキング力が上がったの+IELTSスコアが上がったのは、こちらのBest Teacher。無料体験レッスンはぜひ上をクリック↑(╹◡╹)
4. 終わりに
私の経験を通じて、帰国子女であっても、継続的な学習と適切な環境がなければ英語力を維持するのは難しいことを実感しました。TESOLの理論を学んだ今、自分の子どもにはより良い環境を提供したいと考えています。この記事が、バイリンガル育児に困っている方、英語学習に悩む方や帰国子女をもつ保護者の方の参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました(╹◡╹)





